ミナペルホネンが問う「成長」のかたち
みなさんは「ミナペルホネン」というブランドをご存知ですか。私はまったく知りませんでした。アパレル企業の苦闘が続いていますが、ミナペルホネンの創業経営者である皆川明氏のブランド経営は、ファッション産業がサステイナブル(持続可能)に再生するための大切な示唆を含んでいるように思います。
2021年11月14日付け日本経済新聞電子版に掲載された記事より、
”大量につくられ、買われ、そして大量に捨てられる。こんな前提のアパレル産業がぐらついて久しい。売れ残りやセールを見越した価格設定を消費者は見透かし、年50万トンを超える廃棄物は明らかに環境へ負荷をかける。「いま着ている服、買おうとしている服は本当にサステイナブル(持続可能)ですか」。こう問われる時代が近く来る。”
”業界では、顧客の年齢層に合わせて同じ世代・性別のスタッフによる接客が主流だ。創業者兼デザイナーを務める皆川明(54)が運営するアパレルブランド「ミナペルホネン」の各店には世間の定年をだいぶ超えて働く販売員が多くいる。そこに皆川の哲学がにじむ。皆川本人は創業時から何もスタンスを変えていないと笑う。むしろ、持続可能性を強く意識した経営モデルに時代が追い付いてきたように思われる。”

”皆川は1995年に自身のブランド「ミナ」を立ち上げた。自らミシンを踏んで最初に作った服は10着。セレクトショップに自分で売り込みをかけたが、まったく売れなかった。海外ブランドが圧倒的な知名度と人気を誇っていた時代だけに、無名な皆川の作品への反応は極めて薄かった。しかし、やがて鳥や蝶、花などをモチーフに皆川自ら生み出す独特の絵柄が着実にファンを広げ、2000年に東京・白金台に店を構えた。2003年、フィンランド語で蝶を意味する言葉を加えて「ミナペルホネン」に改名。その後はパリコレクションに参加し、著名デザイナーへの登竜門である毎日ファッション大賞を受賞するなど00年代を通じて世間の注目を集めるようになっていった。”
“同じころ、アパレル業界にはバブル崩壊後のデフレによる荒波が押し寄せた。多くの企業が参考にしたのはユニクロのビジネスモデル。しかし、同社のように川上から川下まで一貫してコントロールできたのは皆無に等しい。多くは企画やデザインを商社に任せ、生産は人件費の安い中国などに移し、流行を後追いした商品を短い納期で大量に市場に出すようなビジネスだった。それは皆川の目にはまるで魅力的に映らなかった。今年着て来年ゴミになるような服、そんなものは作らない。だからセールもしない。同じデザインを定番化して何度でも使う。売った商品はたとえ靴下でも修理する。こうした手法を貫いた。”
“商品の値決めの仕方も皆川なりの哲学に基づく。一般的なアパレル企業だと、原価に対して掛け率を設定して商品代金を決める。例えば原価の高いコートやジャケットなど「重衣料」の方がより多くのもうけを生み出す仕組みだ。一方、ミナペルホネンはどんな商品でも、原価に対して一定の金額を利益分として上乗せする。原価の高い商品ほど、顧客からするとお買い得になる。”

”デザインも同様だ。皆川は顧客に支持されたデザインを何度でも使う。「フォレストパレード」と呼ばれるデザインがその一例。花や鳥といった絵柄が37個並ぶレースは、水溶性の布に刺しゅうを施し、最後に溶かして刺しゅう部分だけを残す。着る人の動きに合わせ、「揺れるように動く」特徴を持つ。高度な技術と長い作製期間がかかるため、生産を担う工場からすれば1シーズン限りで発注されても引き受けられない。皆川がこれを定番として使い続けることで、工場も本腰を入れて高品質な物作りに取り組むことができる。”
”「同質化のワナ」。効率化を急ぐあまり多くのアパレルブランドが陥った現象だが、皆川の人生には無縁だ。生地の段階から自らデザインし、協力工場に頼んで自社生産を続けてきた。服を作るため生地を切り抜いていくと15%程度が残るというが、皆川らはこれを小物や家具に応用して徹底して使い切る。これらは全て利益率の改善につながる。”
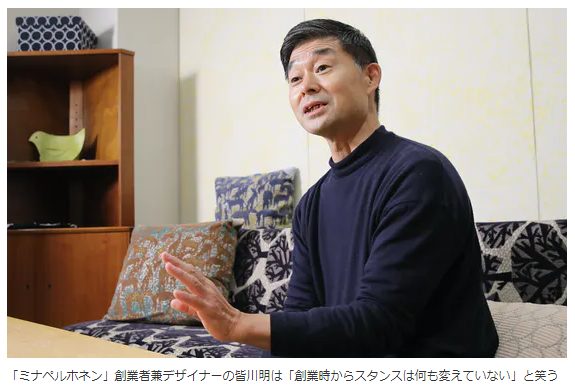
“小売店からの引きは強く、ビジネスを大きくしようと思えばいくらでもできた。けれども安易な拡大路線は歩まなかった。実は自ら成長率にキャップまではめている。年間売上高は2割増まで。これを超えて数字を伸ばせばどこかに無理が生じる。社内だけでなく協力工場や顧客も含めた全ての関係者のうち、どこかに過剰なシワ寄せがいけば、その人は離れて行ってしまう。それが分かっているからだ。”
”「変えるのはそんなに難しいことではないです。経営者の考え一つで今すぐにでも変えられますよ」。変えるべきこと、変えてはいけないこと。これらをきちんと整理しながら激動下を歩んできた皆川の言葉は、問題を認識しながらも「変われない理由」を探し続ける多くのアパレル企業に突き刺さる。(敬称略)”

